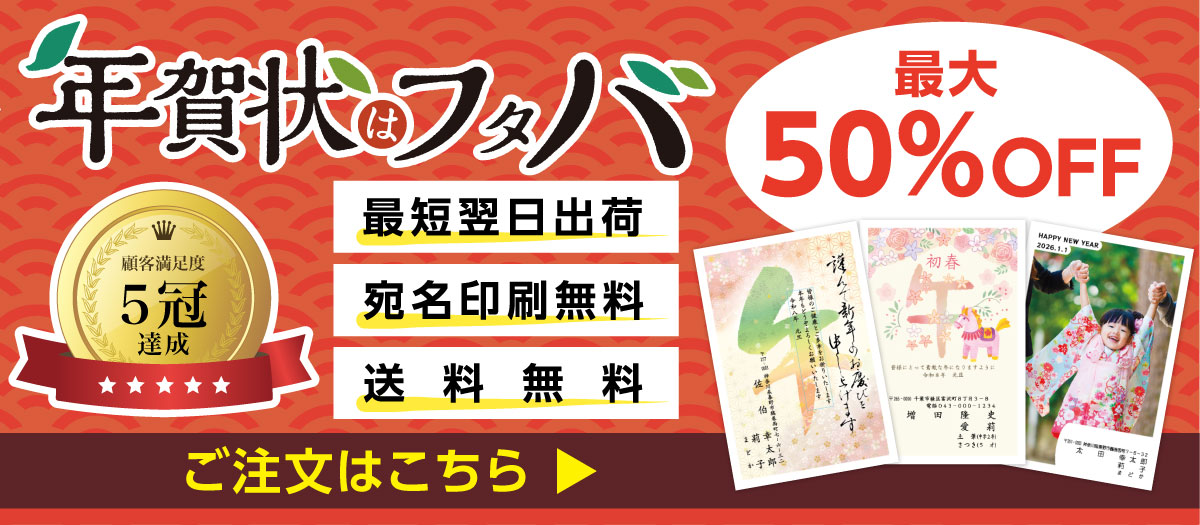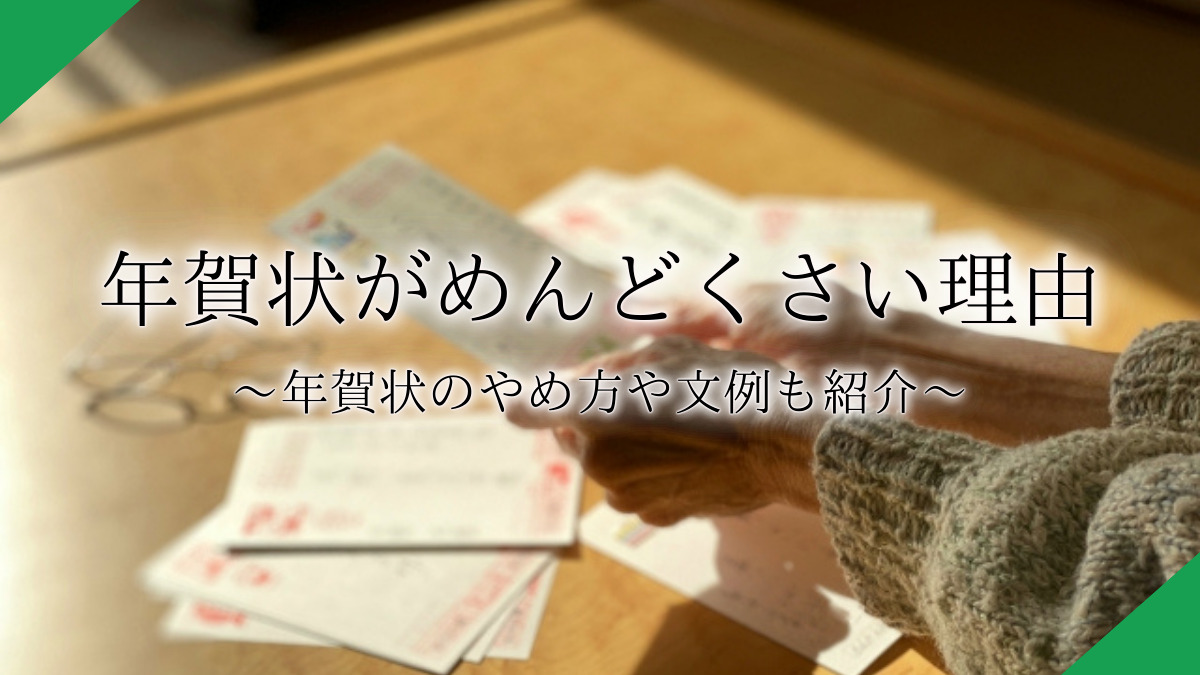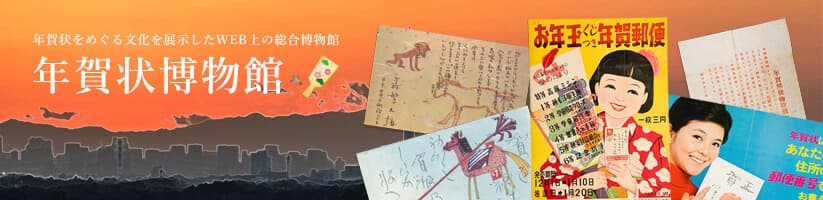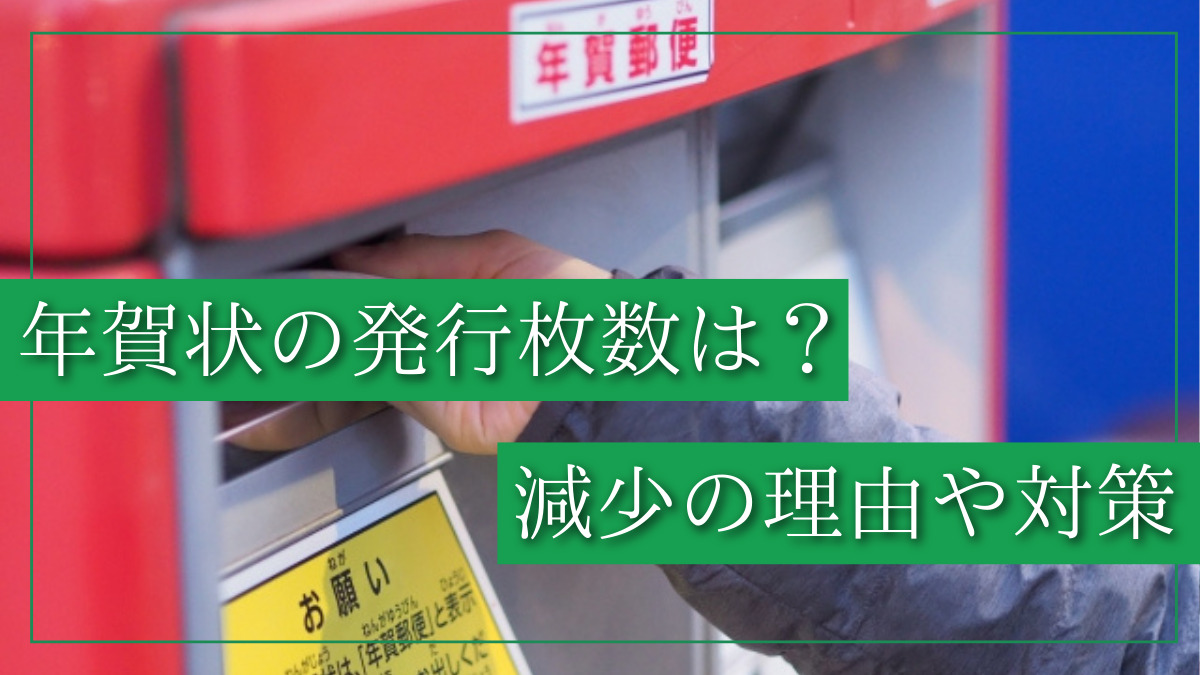
2025.11.20
年賀状はどれだけ減少している?減少している理由やそれに対する対策について紹介
年賀状について
年賀状の発行枚数は年々減少しており、その背景にはメールやSNSの普及が大きいと言われています。
また、昔に比べて住所をかんたんに知ることができなくなったことも要因の一つです。
今回は年賀状の枚数の減少について紹介します。
年賀状の発行枚数は減少傾向
2025年度用の当初発行枚数
日本郵便は、2025年用の年賀はがきの当初発行枚数を前年比25%減の10億7,000万枚とする発表をしました。
前年からの減少率は過去最大となり、年賀状離れが加速していることを物語る結果となりました。
年賀状の発行枚数減少の背景には、メールやインターネット交流サイト(SNS)の普及が大きいとされているほか、10月にはがきが63円から85円に値上げされたことによる需要の落ち込みも大きな要因とされています。
参考URL:年賀はがき 当初発行枚数 前年より25%減 減少率は過去最大に
2010年-2025年はずっと減少
年賀はがきは1949年に発売が開始されてから徐々に発行枚数を伸ばしていきました。
1964年には10億枚、1973年には20億枚を突破し、ピーク時の2003年には44億5,936万枚もの枚数の年賀はがきが発行されました。
2003年をピークに、2010年までは減ったり増えたりを繰り返していたのですが、2010年から現在まで、年賀状の発行枚数は減少し続けています。
1人当たりの年賀状の枚数は半分以下にまで減少
2003年に年賀状の発行枚数が44億5,936万枚と最高になりましたが、2020年には19億4,198万枚にまで減少してしまいました。
1人当たりの年賀状の枚数も同様に、2003年がピークで1人当たり35枚となっています。
そこから徐々に1人当たりの枚数が減っていき、2024年度は過去最低の9枚となってしまいました。
年賀状の1人当たりの発行枚数が最高だった2003年と比べると、3分の1以下の枚数にまで落ち込んでしまったということになります。
年賀状の枚数が減少していく理由
メールやSNSが普及した
年賀状離れが進む原因としてよく挙げられるのが、SNSの普及です。
2020年に総合筆記具メーカーの株式会社パイロットコーポレーションが調査したアンケートでは、新年の挨拶に使うツールで「LINE等メッセージアプリ」(74.7%)が「年賀状」(60.7%)を上回る結果になりました。
次いで「メール」(38.1%)、「Facebook」(14.7%)、「Twitter」(12.6%)、「電話」(9.2%)、「Instagram」(8.4%)となっており、年賀状をわざわざ送らなくても手軽に連絡が取れるため、年賀状の利用が減っていると考えられます。
また、SNSは住所を知らない相手であっても挨拶を送ることができます。
SNSは送るための準備もいらず、年賀はがきのように購入費用も不要なので、送りやすいことが年賀状よりも人気になっているのではないでしょうか。
ただし最近は、SNS上で知り合った本名や住所を知らない相手にも年賀状を送ることができるサービスも誕生しています
お金と手間がかかる
年賀状を送るためには、まず年賀はがきを購入するためにはがき代が必要になります。
ネットの印刷サービスや町の印刷屋さんに年賀状の印刷を依頼する場合、店舗へ足を運んだり、自作のデザインのレイアウトを考えたりと何かと時間や手間がかかるだけでなく、印刷費用もかかります。
自宅で作成する場合はプリンターやインクが必要ですし、場合によっては買い替えなければならないこともあります。印刷するのにも設定が必要だったり、印刷ミスが発生したりするなど時間もかかります。
このように、「わざわざお金や手間をかけてまで年賀状を出さなければならないのだろうか?」と考え、そこまでする必要はあまりないのでは、と感じる人達が増えてきたことが、年賀状を出す人たちが減少した要因の一つです。
年賀はがきは一枚85円に
年賀はがきは消費税の増税、郵便事業の収支改善などを理由に2019年に63円、2024年には85円にまで値上がりしました。
1枚あたりの年賀状の金銭的負担が増えた事から、これをきっかけに年賀状を出すのをやめたり、年賀状を出す枚数を減らしたりする人が増えました。
住所を知らないことが増えた
最近では個人情報の扱いについて厳しくなり、以前のように簡単に住所を知ることができなくなりました。
数十年前までは、学校の連絡網や卒業アルバムのほか、社員名簿などに名前と一緒に住所が載っているのが当たり前の時代でした。
しかし現在のように、直接本人に教えてもらわないことには住所を知ることができないとなると、わざわざそんなことをしてまで年賀状を出すこともないという風に考える人が増えてきた、というように考えられています。
年賀状が減少していることへの対策とは?
お年玉抽選くじの1等賞品(現金)の金額増加
減少し続ける年賀状への対策として、2013年発行分のお年玉付き年賀はがきから、お年玉抽選くじの賞品の内容に現金賞品がくじの商品に加わりました。
さらに、2015年に発行された2016年度用の年賀はがき以降は賞金が10万円に底上げされることとなりました。しかしその一方、当選確率は1/10の「100万本に1本」に低下してしまいました。
さらに2019年に発行された2020年度用の年賀はがきからは、当選確率はそのままで1等賞品の現金の金額が10万円から30万円に大幅に上昇しています。
投函代行サービス
投函代行サービスとは、ネットの年賀状印刷サービスで年賀状の作成・印刷だけでなく投函までしてもらえるサービスです。
自宅で年賀状を作成して印刷する場合は、まず年賀はがきを購入して、その後に自分でプリンターの設定やインクの補充をしなければなりませんでした。
ですが投函代行サービスを利用することで、自宅にいながら年賀はがきの購入から年賀状の印刷、配送までを完了させることができます。
年賀状スルーとは
2019年頃から「終活年賀状」「年賀状じまい」に加え、「年賀状スルー」という言葉が注目されるようになりました。
年賀状スルーとは名前の通り、年賀状をもらっても出さないことを指します。
スルーは「無視する」という意味があるので、年賀状そのものの存在を無視してしまおうというような意味で使われています。
年賀状スルーをする人には大きく分けて3つの理由があります。
①年賀はがきの1枚85円が高いと感じる
②相手の住所を知らない
③年賀状を書く時間と手間が負担に思える
また、最近は個人情報を気にするという人も年賀状を避ける傾向にあるようです。
年賀状スルーは若者だけの話ではありません。
世間では会社ぐるみで年賀状をやめたところも多くあり、「何百枚も年賀はがきにお金を使うことは無駄な経費であると判断した」という理由があるようです。
「年賀状は出すことが常識である」という考えから徐々に変わってきているのでしょう。個人も法人も年賀状は出すことが常識という概念は薄れてきています。
年賀状は出さなくてもよいという新しい考えにより、今後も年賀状の発行枚数は減り続けていくと思われます。