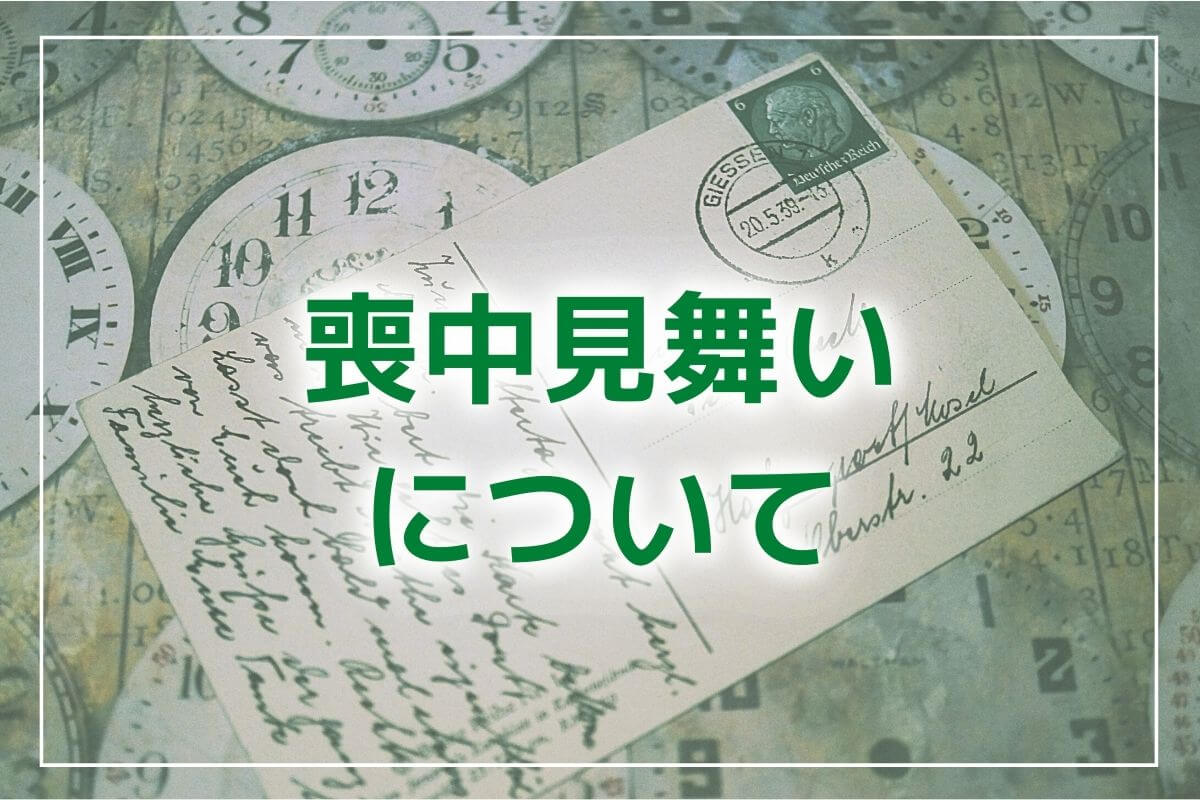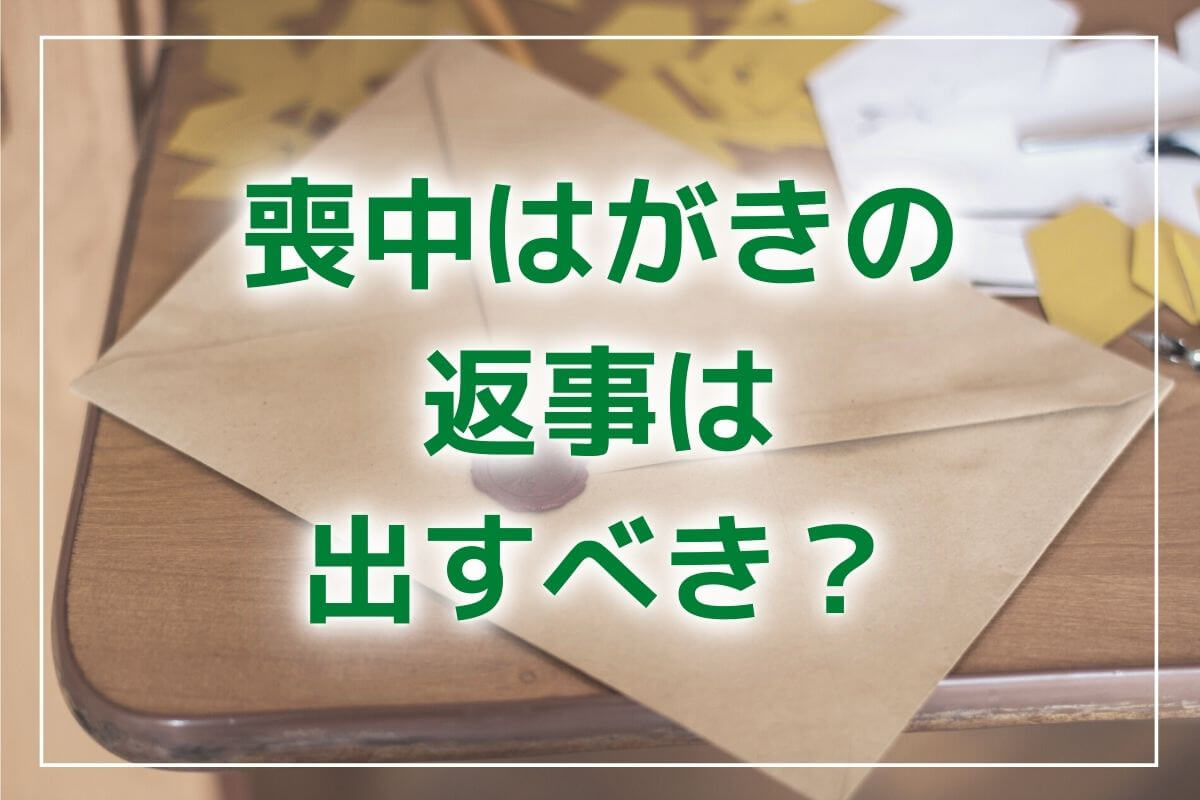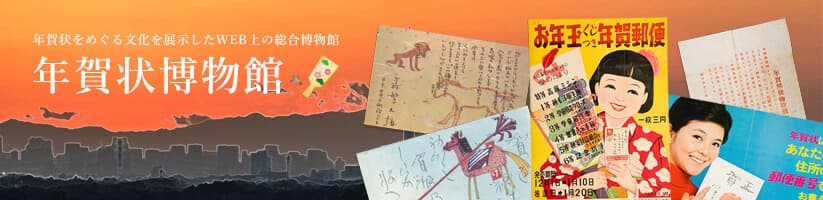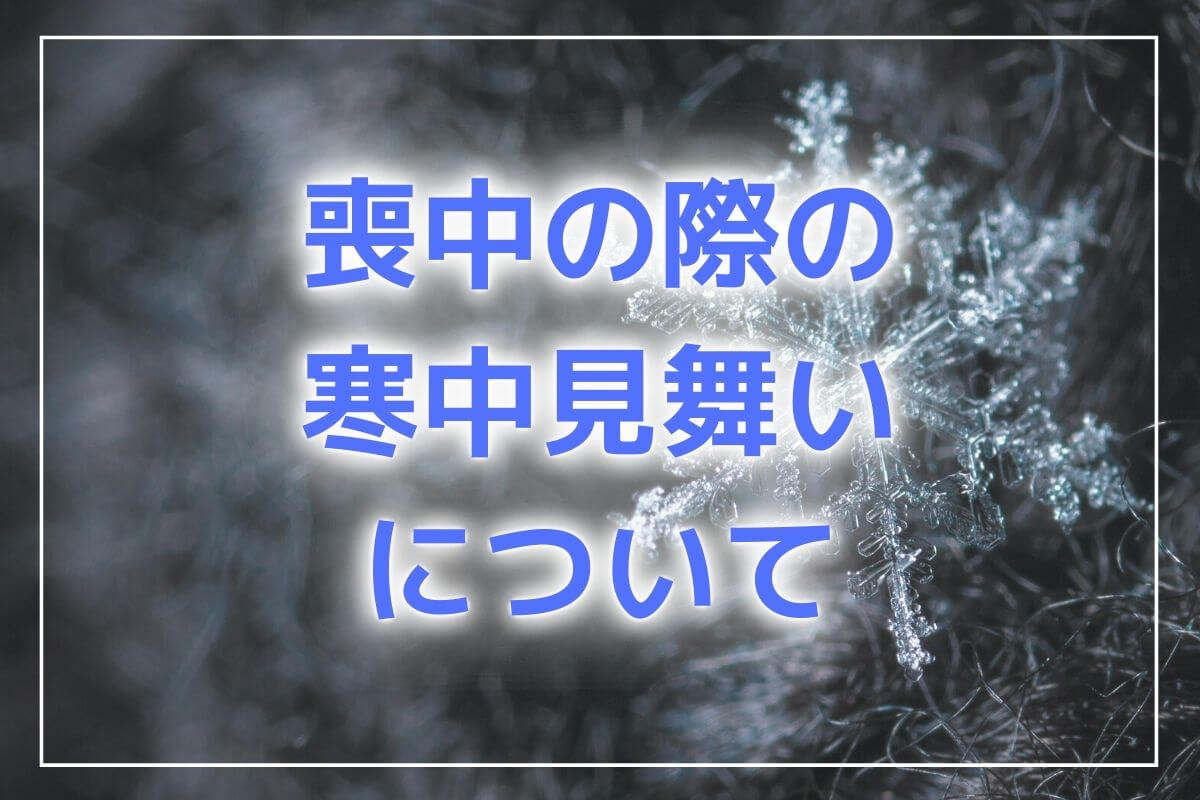
2022.10.31
寒中見舞いは喪中はがきの返事として出せる?違いや喪中の寒中見舞いのマナーも紹介
喪中はがき
寒中見舞いは、喪中はがきを貰った後の返事として出すこともできます。
しかし、寒中見舞いを出す際にはマナーなどに気を付けなければいけません。
今回は、喪中の際に出す寒中見舞いのマナーなどを紹介します。
寒中見舞いを出す際には、フタバの寒中見舞い印刷サービスを利用すれば、マナーを守った寒中見舞いを簡単に印刷することができますよ。
スマホから5分で注文することができるので、忙しい方でも安心です。
【はじめに】喪中はがきと寒中見舞い、どう違う!?
まずは以下の表を参考に、喪中はがきと寒中見舞いの違いを正しく理解しましょう。
| 喪中はがき | 寒中見舞い | |
|---|---|---|
| 誰が送る? | 喪中の方 | 誰でもOK |
| 送る目的 | 年賀欠礼の挨拶 | 季節の挨拶 |
| 相手に届ける時期 | 11月~12月の初旬まで | 1月8日~2月4日まで |
両者には上記のような違いがありますが、寒中見舞いは「喪中の方への挨拶状」もしくは「喪中の方が用いる挨拶状」として、喪中に関するケースで使われることが増えています。
寒中見舞いは喪中の方にも送ることができる
先述のように寒中見舞いは、喪中の方に送っても問題ありません。
そもそも、寒中見舞いとは季節の挨拶として送られるものだからです。
季節の挨拶状には、寒中見舞いのほかにも暑中見舞いや残暑見舞い、余寒見舞いなどがあります。
最近では、寒中見舞いを喪中の方に送ったり、年賀状を松の内である1月7日までに出しそびれた際の返礼に使われたりすることも多くなっています。
また、喪中はがきの返事として送ることや、喪中と知らずに年賀状を出してしまった場合のお詫びとして送られることも増えてきました。
喪中はがきのお返事として
喪中はがきをいただいた相手へ、年始の挨拶がわりとして「寒中見舞い」を送ることができます。
喪中の相手に年賀状は送れませんが、追悼の意味を込めたり近況を伝えたりする目的で活用するとよいでしょう。
なお、年始の挨拶がわりとして寒中見舞いを送る際には、その時期に注意が必要です。
松の内である1月7日を過ぎた1月8日以降から立春を迎える2月4日までの間に相手の元に届くように送りましょう。
喪中と知らずに年賀状を出してしまったお詫びとして
相手が喪中と知らずに年賀状を出してしまった場合は失礼には当たりません。
しかし、お詫びとして1月8日以降に「寒中見舞い」を送ることは、より丁寧な対応だといえます。
年内に喪中であることが発覚した場合は、年内のうちにお詫びの連絡をしておきましょう。
その後、松の内が過ぎた頃に再度寒中見舞いとしてお詫びやお悔やみの言葉を述べて送付することをおすすめします。
喪中の方でも寒中見舞いを送ることができる
先述の通り、喪中の方にも寒中見舞いを送れますが、喪中の方が寒中見舞いを送っても問題ありません。
喪中はがきを送るのが間に合わなかった場合
年内に喪中はがきを送ることができなかった場合は、「寒中見舞い」という形で喪中の旨を相手に伝えることができます。
年末近くになって身内に不幸があると、喪中はがきが間に合わないことがほとんどです。
そのような場合は、年内ギリギリに喪中はがきは出さず、寒中見舞いを送るようにしましょう。
喪中の際に年賀状をもらった方へのお返事として
喪中の際でも年賀状が送られてくることはあります。
多くの場合は、喪中はがきを出していない、または出し忘れた相手から年賀状が届くケースです。
なかには亡くなった方の友人や知人など、喪中はがきを出していなかった相手から届くことがあります。
喪中に年賀状を受け取ることは何の問題もありませんので、より丁寧な対応として年賀状に「寒中見舞い」で挨拶を返すとよいでしょう。
喪中に関する寒中見舞いを出すときのマナー
喪中はがきや年賀状に比べて比較的少ないですが、喪中に関する寒中見舞いを出すときにも少なからずマナーがあります。
年賀はがきは使わない
年賀状の挨拶代わりの寒中見舞いだからといって、年賀状を使うことは適していません。
寒中見舞いに使ってもよいのは「郵便はがき」もしくは「私製はがき」です。
郵便局はもちろん、コンビニエンスストアや大型のスーパーなどでも購入できます。
年賀状が余っている場合でも、寒中見舞いとして使用しないように注意しましょう。
余った年賀状を使いたい場合は、郵便局で1枚5円の手数料を払えば通常のはがきや切手などに交換できるので、ぜひ活用してみてください。
切手は普通切手を使う

私製はがきを使用する場合には切手を購入し貼る必要があります。
喪中に関する寒中見舞いを送る場合は普通切手を選びましょう。
郵便局の切手に印刷されている絵柄には、山桜や胡蝶蘭、タンチョウ、ヤマユリの4種類があります。
基本的にはどの絵柄を選んでも問題ありませんが、弔事のお知らせではないため、弔事用の切手を貼るのは適していません。
また、結婚式やお祝いごとの郵便物に使用される慶事の切手もふさわしくないので、控える必要があります。
デザインはシンプルなものを
新年を祝う年賀状とは異なるので、新年らしい干支のデザインや七福神、富士山などの縁起物のデザインは避けましょう。
また、大きな家族写真なども控えます。
一般的には、季節の風景や植物などシンプルなデザインのものが、寒中見舞いとしてふさわしいとされています。
喪中のための落ち着いたデザインのものも販売されているので、活用するとよいでしょう。
書き方のマナー
寒中見舞いの書き方には、いくつかのマナーがあります。
頭語と結語を省略する
「拝啓」「敬具」などの頭語や結語を省略するのが一般的です。
句読点は入れない
儀礼の文書のほとんどに当てはまるルールですが、句読点は入れません。
行頭の一字下げはしない
寒中見舞いは基本的に縦書きで書きます。
縦書きの挨拶状では、行頭に一文字分のスペースをあける必要がないとされています。
賀詞は使わない
新年の挨拶でよく用いられる、「謹賀新年」や「あけましておめでとうございます」といったお祝いの言葉は使ってはいけません。
数字は漢数字で表記
寒中見舞いに関わらず、縦書きの場合は漢数字で書くのがマナーです。
喪中に関する寒中見舞いの文例
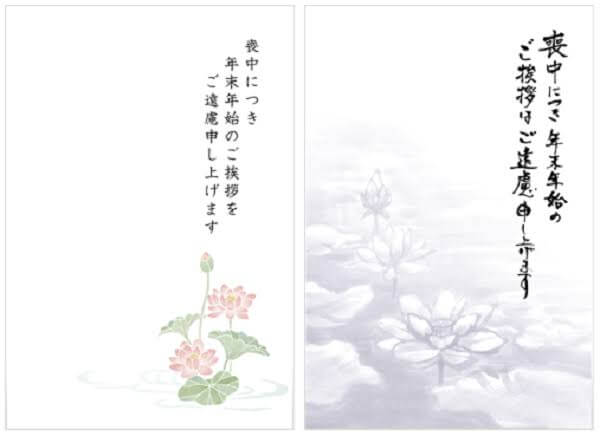
喪中に関する寒中見舞いは、いろいろなケースがあることを冒頭でお伝えしました。
ここでは、それぞれのケースに適した文例をひとつずつご紹介していきます。
喪中はがきのお返事の文例
寒中御見舞い申し上げます
御服喪中と伺い年頭の御挨拶はさし控えさせていただきましたが
いかがお過ごしでしょうか
この度の○○様のご他界を知り大変驚いておりますとともに
謹んでご冥福をお祈り申し上げます。
寒さが一段と厳しくなります折柄
風邪などお召しになられませんようご自愛ください
喪中と知らずに年賀状を出してしまったお詫びの文例
寒中お見舞い申し上げます
○○様ご逝去のこと存じ上げなかったとはいえ
年始の御挨拶を申し上げてしまったことを深くお詫び申し上げます
ご逝去を悼み心よりご冥福をお祈り申し上げます
いましばらくは寒い日も続くかと思いますので
皆様どうかお元気でお過ごしください
喪中はがきを送るのが間に合わなかった際の文例
寒中お見舞い申し上げます
昨年12月に〇〇が〇〇歳にて永眠致しましたため
新年のご挨拶を申し上げるべきところ
喪中につきご挨拶を控えさせていただきました
旧年中にお知らせするところ
年を越してしまいました非礼をお許しください
寒さ厳しき折柄
風邪など召されませぬようご自愛ください
喪中の際に年賀状をもらった方へのお返事の文例
寒中お見舞い申し上げます
このたびはご丁寧な年始のご挨拶をいただき有り難く存じます
新年のご挨拶を申し上げるべきところ
喪中につき年頭のご挨拶を差し控えさせていただきました
連絡が行き届かずに申し訳ございませんでした
昨年中に賜りましたご支援に深く感謝いたしますとともに
今後とも変わらぬご交誼の程よろしくお願い申し上げます
フタバなら寒中見舞いを簡単・お得に印刷できる
ここまで、喪中に関する寒中見舞いについてご紹介してきました。
寒中見舞いを出す際には、はがきの種類や切手のほか、書く内容や書き方などさまざまな点に注意が必要です。
フタバなら、簡単・お得にマナーを守った寒中見舞いを印刷できますよ。
スマホから5分で簡単に注文できる!
デザインと挨拶文のテンプレートの種類を選ぶだけで、スマホから5分で簡単に寒中見舞いの注文ができるので、初めての方でも安心です。
また最短で翌日発送なので、喪中はがきや喪中にもらった年賀状の返事をお急ぎの方にもぴったりです。
フタバなら送料はもちろん宛名印刷も無料!
フタバの寒中見舞い印刷サービスなら、ご自宅への送料や宛名印刷は無料です。
ご自宅での作業に比べて簡単かつお得に寒中見舞いを印刷できるので、ご利用いただいたお客様からも「とても助かっています。」と大変ご好評をいただいています。
フタバのサイトから注文すると最大50%割引
『年賀状はフタバ』のサイトから直接お申込みいただくことで、最大で50%割引の料金でお得に喪中はがきを印刷することができます。
寒中見舞いを出そうとお考えの際には、ぜひフタバの印刷サービスをご利用ください。
まとめ
寒中見舞いは、喪中の相手への新年の挨拶代わりとして送ったり、喪中へのお返事として送ったりすることができます。
寒中見舞いを出す際には、マナーなどに気を付けて出すようにしましょう。